- OKWAVE コラム
- みんなの悩みや疑問が解決したQ&Aをもとに、日常生活や専門分野で役立つノウハウ記事をコラム形式でご紹介。
誰でも気軽に学べる情報をお届けします。
バブルの昭和、日本人はどう生きてた?
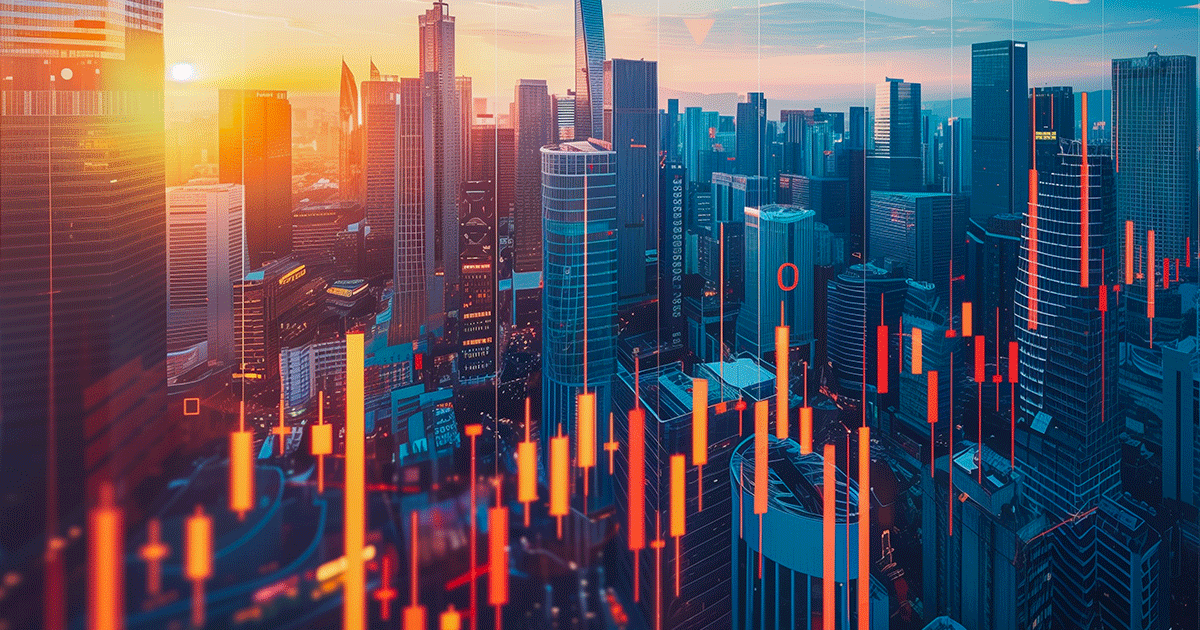
バブルの熱狂と高度経済成長の勢いに包まれた昭和の時代。
その頃、日本人は何を信じ、どんな暮らしをしていたのでしょうか。
OKWAVEで投稿された3つの質問には、当時を知らない若者たちの素朴な疑問と、それに応えるリアルな証言が詰まっていました。
現代とはまるで異なる空気のなかで、人々は何を感じ、何を大切にしていたのか──
過去の声を手がかりに、“あの時代”の輪郭をたどります。
第1章:熱狂と分岐の時代──昭和の成長とバブルの実態
「高度経済成長期やバブル期の頃の日本って、どんな感じの世の中だったんですか?」
──この問いは、OKWAVEに寄せられたある若者の素朴な疑問です。私たちは歴史として昭和を知っていても、そこに息づいていた“暮らし”や“空気感”まで実感することは難しいものです。しかし、当時を生きた人々のリアルな声には、現代の私たちが知るべきヒントが詰まっています。
回答No.1
「給料が毎年3割上がり、3年で倍になった」「日本人がみんな元気でやる気十分だった」
回答No.4
「お金と技術があれば小さな会社が大企業になる夢があった」
昭和の高度成長期は、個人の努力と経済成長が結びついていた時代だった。会社に勤め続ければ給料は着実に上がり、成功も夢ではなかった。社会全体が前向きな熱気に包まれ、「頑張れば報われる」という共通の信頼があった。
回答No.2
「オリンピックや万博などで日本中が上昇気運」「海外旅行やブランドバッグが当たり前になっていった」
回答No.3
「巨人戦が全国放送、9割が巨人・阪神ファン」「流行も一体だった」
暮らしの中にも、その勢いは反映されていた。テレビやブランド品、レジャー、海外旅行――人々は手に届く豊かさを追いかけ、同じ情報や流行を分かち合った。個の時代ではなく、「みんなで一緒に進んでいく」ことに価値があった時代でもある。
回答No.5
「土地が6億円で売れたが、今では3,000万もしない」「波に乗れた人は裕福に、乗れなかった人はそのまま」
ただし、誰もが豊かさを得たわけではなかった。バブルに乗れた人とそうでない人の間には、のちに大きな格差が生まれた。「一億総中流」と言われた時代の裏側には、静かに進行する分断もあった。
回答No.3
「24時間タタカエマスカ」「暴力的な指導も普通だった」
また、長時間労働や精神論に支えられた企業文化には、現代の基準では容認されない慣習も多く含まれていた。昇給と安定が保証される代わりに、厳しさや理不尽さもまた、日常に組み込まれていた。
昭和とバブルの時代は、努力が報われるという実感と、成長への信頼に満ちていた。
一方で、長時間労働や男女の役割分担、同調圧力など、今では見直されるべき価値観も“常識”として受け入れられていた。
昭和の経済成長とバブルの実態は、希望と勢いにあふれていたが、その内側には格差と偏った常識が潜んでいた。
“豊かさ”とは何か――その問いに向き合うためのヒントが、今なおこの時代には残されている。
第2章:バブル期の20代は本当に“余裕”だったのか?
「昭和の高度経済成長期の20代の給料っていくらくらいだったんですか?」
──そんな疑問がOKWAVEに寄せられました。小説に描かれるバブル期の若者は、今とはまるで別世界に生きているように見える。実際の当時を知る人々の声から、その実態を探ります。
回答No.1
「正社員の月給は今の方が高いが、当時はボーナスが2.5〜3ヶ月分。昇給は毎年1万円以上が当たり前」「将来の昇給を前提にローンが組めた」
回答No.2
「1988年入社で総支給19万7,000円。成果主義が強く、働く人も向上心があった」
当時の月給は今と大きく変わらないが、年功序列の昇給制度と高額なボーナスによって将来の収入が約束されていた。その安心感が支えとなり、若者は積極的に消費や投資を行っていた。努力することへの見返りが明確で、自信とやりがいを持って働く空気が社会全体にあった。
回答No.3
「接待費など会社経費が潤沢で、飲み代や合コン費も落とせた」「20代前半で“デート用のクーペ”を買うのが普通だった」
「正社員になれれば、親元から通いながら遊んで貯金もできた。若い人が元気で、金を使うことで社会が回っていた」
バブル期の企業には、今では考えられないほどの経費枠があり、それが若者の生活に直接還元されていた。仕事の延長線上にある遊びも“経済活動”として成立し、若者は車やファッション、レジャーに堂々とお金を使った。その消費がまた景気を押し上げる――そんな好循環の真ん中に20代がいた。
回答No.3
「今は正社員になるのが難しく、お金を使いたくても使えない」「当時は“将来も安泰”という前提があった」
当時の20代には、今の若者には想像しにくい“根拠のある楽観”があった。昇給・終身雇用・景気の右肩上がりという時代背景が、若者の心理にも強い安心感を与えていた。一方、現代は将来の見通しが立ちにくく、お金を使いたくても使えないというジレンマがある。
バブル期の若者が特別裕福だったわけではない。しかし、働けば報われ、将来は今より良くなるという共通の確信があったからこそ、消費が楽しさと余裕を生み出していた。
“豊かさ”は金額の問題ではなく、将来への信頼と使うことへの自信から生まれていたのかもしれない。
第3章:私たちは何を置き去りにしてきたのか──昭和が問いかけるもの
「高度経済成長の時代に今の日本人が忘れてきた物って何だと思いますか?」
──この問いは、昭和を経験していない若者からOKWAVEに寄せられたものです。成長と希望に満ちていたはずの時代。そこに生きた人々の言葉から、私たちが見失ってしまったものを見つめ直します。
回答No.6
「忘れてきたのは“謙虚さと感謝の心”。それがないと人は敬えず、学べず、周囲にも害を及ぼす」
回答No.4
「昔は、金持ちが偉いという価値観はなかった。貧乏も恥ではなかった」
当時の人々は、他者や社会に対する敬意と感謝の意識を持ち合わせていた。お金や地位よりも人間性を重視する感覚が今より強く、物事を“まっとうに生きる”ことに価値が置かれていた。現代では当たり前になった利己的な評価基準とは対照的である。
回答No.3
「豊かになるたびに驚きや喜び、感謝があったが、今ではそれが当たり前になり、不満につながっている」
回答No.2
「苦労して育った親が、苦労知らずの子を育て、その子がいま苦しんでいる」
高度成長の中で得た豊かさに、人々は率直に喜びを感じていた。しかし、その感情は世代を超えて伝わりにくく、やがて“豊かさが前提”の時代に変わった。何かを得るたびに感謝する姿勢が、少しずつ薄れていったのかもしれない。
回答No.5
「公害を見れば、国も企業も人命を軽視していた。社会もそれを許容していた」
回答No.1
「今の人たちは道草を食わない」
経済成長の裏には、命や環境を犠牲にしてでも前に進むという無理があった。目の前の成長に夢中になり、立ち止まって振り返ることが忘れられていたのかもしれない。心の余白やゆとり――そうした「道草」の時間も、いつの間にか見失われていった。
高度成長期は確かに、希望と活気にあふれた時代だった。だがその裏では、感謝や謙虚さ、立ち止まる余裕といった大切な感覚が、少しずつ後ろに置き去りにされていった。
物が満ちた今だからこそ、“心の豊かさ”とは何かを見直す視点が、私たちには必要なのかもしれない。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
OKWAVEに寄せられた質問と、当時を生きた人々のリアルな声から見えてきたのは、昭和とバブル期の日本にあった確かな勢いと希望、そして今では見えにくくなった価値観でした。
“豊かさ”とは何か――答えはひとつではありませんが、時代の変化に埋もれてしまった感覚や意識の中に、これからを考えるヒントが眠っているように感じます。
OKWAVE で質問してみる?
聞きたい事が浮かんできたら質問してみませんか?
OKWAVEでは、毎月4000人が参加しています。あなたの悩みも解消できるかも!?






